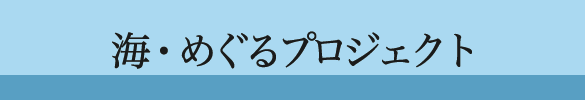水産界 連載記事 1594号 2017年11月 掲載
「ブランド魚」の「ブランディング」
今日のメイン料理は、干物だ。義母の講演を企画した会社から、講演のお礼として贈られてきたものだ。「見て!印がついていますよ」
ふっくらした魚の身には、焼印が押してある。高級感もあり、見るからに美味しそうだ。
焼印は、ブランドの語源でもある。
「お義母さん、ブランド魚ってこの頃よく聞きますけど、何ですか?」
「地域で獲れたものとか養殖ものを、ブランド魚って言って売っているのよ、私も相談されたことがあるわ」
「特産品とか、名産品ではダメなんですか」
「特産品でもいいんじゃない、鮮魚より加工品の方がブランドになりやすいと思うんだけどね」
義母は「90歳、魚を食べて健康」を自負する水産加工食品や魚食に関わる研究者、「鈴木たね子」である。私は、ブランド構築や海外ブランドのプロモーションを手がけてきたせいか、どうしても「〇〇ブランド」の魚の方がしっくりくる。
しかし「ブランド魚」とはよく考えたものである。マーケティング的には、ブランドもののシャツやジャッケットなどブランドを構成するアイテム(品目)に当たるものだ。ブランドの「信頼」や「高品質」というイメージを使ったコミュニケーション手法である。しかし、ブランドを活用した戦略であるならば、そのリスクも知っておくことが大事だ。ブランド戦略の最大のリスクは「陳腐化」である。陳腐化とはブランドに新鮮味がなくなると商品の魅力が薄れ、ブランドそのものが飽きられてしまうこと。ブランド戦略では、あらかじめ陳腐化の対策を立てておいたり、あえて陳腐化を計画的に行うこともある。この陳腐化対策の一つが「ブランディング」という手法である。
そもそもブランドとは、ヨーロッパの馬具屋が自分が作った証として、製品に「焼印=brand」を押したことがはじまりである。作り手がものづくりのこだわりとポリシーを印したのである。吟味した素材、洗練された加工技術、製品の完成度、そして流通・販売まで、品質の一環性を証明するものである。
魚のブランド化は、「関あじ」、「関さば」の商標化(1996)に見られるように、偽物対策や資源管理、流通のコントロールを含めて「価値」を維持するための手法として知られるようになった。その一方で、ブランド魚は高額で取引できることが知れ渡り、スーパーマーケットの「販売手法」として定着していく。生産者としては、差別化することで産品に高値がつくこと、販売側は、ブランドのレッテルがあれば商品説明の人材や手間が省ける、という双方の利益が一致した結果である。しかし、売り易さばかりにとらわれ、本来の質の高い産品を届けるという生産者のこだわりを欠いてはならない。ブランドは、生産者と消費者との「品質の約束」なのだから。そして、販売者は消費者の疑問にも応えなければならない。沖で獲ってきた魚がなぜブランド魚になるのか、ブランド魚とノーブランドの魚の違いは何か、ブランド魚以外の魚は品質が悪いのか…。 消費者は嘘のない商品を求めているのだ。
ブランド魚は、「品質」と「差別化」を基本としたマーケティングである。この先、同じようなものがいくつもブランド魚として出回るならば、差別化としての機能も薄れてしまい、消費者には売るための仕掛けとしか映らない。結果、鮮魚への不信感を募ることになる。それは一ブランド魚ばかりでなく、ブランド魚全体の価値をも低下させる。このようなブランド魚の陳腐化の影響は、魚食全体のマーケットに及ぶことも否定できない。
「ブランド魚は、地域の産品価値を高める手法である」として、各地でブランド化の取り組みが盛んに行われている。であるなら、ブランド魚に関係する人々は、共倒れを未然に防ぐために、そして市場価値を落とさないためにも「ブランド」とは何かという原点に戻り、ブランド魚の定義を明確にしておく必要があるのではないだろうか。輸出も視野に入れているならば尚更である。
ブランド魚の乱立による陳腐化が心配される今だからこそ、ブランド魚のブランディングが求められているのだ。それは何よりも消費者の信頼を得るために重要なことである。また、ブランド魚には資源や環境を守るという大事な側面があるはずである。魚食の未来をつくるためのブランド魚の再構築、そのブランディングに期待したい。
シーフードを身近にする流通新業態
経済産業省「商業統計」によれば、2000年〜2009年の10年間で、家庭内での魚介類の消費割合は20ポイント以上減っている。魚屋の数もほぼ同期間において約30%の減少だ。さらに、日本チェーンストア協会調べ(2004-2013)では、スーパーマーケットでの魚介類の売り上げも20ポイント下がっている。これらのデータから見て、スーパーマーケットは魚屋の受け皿にはなっていないことが分かる。
魚屋は、鮮魚のバリエーションが多く、それが季節によって変わる。選び方や食べ方も教えてくれるなど、消費者に魚食の魅力を伝える役割を担っていた。それがここ20年間になると、60%も減っているのには驚きである(経産省商業統計速報平成26年)。20年前というと1997年、共働き世帯が片働き世帯数をはじめて上回った年でもある。
この年を堺に共働き世帯の方が多くなって行く。消費者の「働き方やライフスタイルの変化」が、身近にあった魚屋を遠い存在にしてしまったのである。消費者のライフスタイルとの接点がなくなることで、鮮魚との距離感が生まれたのだ。
この消費者との距離感に着目したのが大手スーパーイオンである。「まいばすけっと」という新しい業態で、近隣の高齢者や歩いて買い物する人を取り込んで行った。会社帰りに立ち寄れる身近なイオンの店が、共働きの世代からも支持され、今では、首都圏を中心に600店舗以上に広がっている。
水産食品のマーケットにおいても、共働き世帯の消費行動や嗜好性、食のスタイルの傾向を掴むことで、これからのチャネルの在り方や販売スタイルが自ずと見えてくるはずである。さらに共働き世帯との「共感」を軸に、彼らの利便性に応える販売方法や品揃え、そしてサービスや情報発信の在り方などを検討することで事業性も判断できる。 課題解決のテーマは、「魚食を消費者の身近に」である。魚食と消費者との距離感を縮めることが大事だ。オフィス街にある「シーフードデリ」、ショッピングセンターの中の「シーフードカフェ」、地元の駅にある「シーフードスタンド」など、新業態の登場も期待できる。行く先々でシーフードと出合え、場所場所で手軽に入手できる仕組みがあれば、魚食はもっと身近なものになるはずである。
旬の鮮魚、こだわりの加工品、一ひねりしたデリ、数々の薬味(ハーブ)。一歩足を踏み入ればシーフードワールドを堪能できるオシャレな魚屋、そんな店の顧客になることが、水産に永く関わってきた義母の夢でもある。ト・フィッシュ」として、その価値を再評価し、リ・コミュニケーションすることで、水産加工食品がスタイリッシュな食材として若い世代に受け入れられる可能性が見えてくる。
鈴木たね子(すずき・たねこ)氏 プロフィール
農林水産省研究機関を経て、日本大学教授、国際学院埼玉短期大学教授。大日本水産会おさかな普及学術諮問会議座長、海洋開発審議会委員等を歴任。 現在は、国際学院埼玉短期大学客員教授、おさかなマイスター協会講師。「健康のための食生活」をテーマに、執筆、講演活動をしている。著書に『なぜ、魚は健康にいいと言われるのか?』(成山堂書)、『お魚を毎日食べて健康になる』(キクロス出版)など多数。