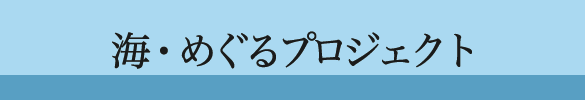水産界 連載記事 1592号 2017年9月 掲載
コミュニケーション・ロス?
わが家の食卓は、マーケティングのリサーチの場になることがある。魚が食卓に上ると、義母と水産業界の話で議論になることも多々ある。義母の名は「鈴木たね子」。水産加工食品の専門家で御年90歳。まだまだ元気で、魚と健康に関わる本の執筆や講演などで飛び廻っている。おおらかで優しい人だが、魚食の話になると少しムキなるクセがある。今日のわが家の食卓は、タラのフリットと赤ワインだ。一見オシャレに感じるが、わが家の手抜き料理の一つである。
「お義母さん、魚食普及って何を意味しているんですか?」
議論のゴングを鳴らす。常々疑問に思っていたことを投げかけてみた。私の仕事は、ブランド構築やマーケティング戦略が専門。ライフスタイルの変化や嗜好性、感性など、生活者マインドとブランドや商品の関わり方がすぐ気になってしまう。それで「普及」という言葉が持つコミュニケーション上での役割や、「普及」が示唆する魚食のスタイルとは何かなどに、興味が湧くのである。
「知らないの?!消費が落ちたから、もっと魚を食べてもらおうと水産業界で頑張ってるのよ」
何やら消費回復のための啓発活動らしい。
「日本人は昔から魚を食べてきた訳ですから、魚食は普及してるんじゃないですか?」
すかさず切り返す。

「ところが魚食離れが結構深刻で、期待されていた高齢者もそれほどじゃないのよね」
なるほど、それは想定外だ。しかし、考えてみれば、今は20〜30年前よりも食材が豊かで、食事のスタイルも多様化している。魚か肉かという二者択一の時代ではない。
「魚食を全体として捉えないで、鮮魚、加工食品などに分けて、何をどの世代に、と絞り込んでみたらいいと思いますよ」
「世代ごとのライフスタイルの分析は、当然してますよね」
と突っ込んでみた。
「簡単に言うけれど、調査もしてるし水産業界としてはやれることは全部やってきたのよ」
なるほど、それは想定外だ。しかし、考えてみれば、今は20〜30年前よりも食材が豊かで、食事のスタイルも多様化している。魚か肉かという二者択一の時代ではない。
「魚食を全体として捉えないで、鮮魚、加工食品などに分けて、何をどの世代に、と絞り込んでみたらいいと思いますよ」
「世代ごとのライフスタイルの分析は、当然してますよね」
と突っ込んでみた。
「簡単に言うけれど、調査もしてるし水産業界としてはやれることは全部やってきたのよ」
マーケティングでは、提供する商品やサービスが、生活者のQOL(クオリティ・オブ・ライフ=暮らしの質)に役立つこと、そして提供の仕方がターゲットのライフスタイルに合っているかということを重視する。有機野菜の場合で例えると、「食の安全・安心」をテーマに、時間のない「子育て世代」に対して「宅配」で届けるという、利便性を付加価値にした戦略となる。有機野菜は、この子育て世代の支持をベースに、共働き世代へと普及し、市場形成に繋がっていく。
義母が力説するように、業界はあの手この手を尽くしてきたことと思う。しかし、情報を発信する業界とそれを受け取る消費者の間には、何かしらの乖離があるのではないか、という疑問が生じてくる。「魚食普及」とは、誰に向けた普及策で、対象としているのは鮮魚だけなのか、加工食品は入らないのか、訴求しているのは調理法なのか、それとも新たなメニューの提案なのかと、受け手は迷ってしまう。消費が思うように回復していないことを考えると、そこに「コミュニケーション・ロス」が起きているのではないかと心配になる。
情報を発信しているのに、伝えたい人に伝えたいことが届いてない、あるいは本来伝えたいことが違うものに置き換わってしまうことがある。これをマーケティングでは、「コミュニケーション・ロス」と呼ぶ。
「魚食普及」のコア・ターゲットを食卓の要になっている女性とするならば、彼女たちのライフスタイルに合った情報発信やノウハウの提供こそが「魚食普及」の鍵である。さらに、購買に結びつく仕組みもなければ、普及には繋がらない。果たして彼女たちに意図した情報は間違いなく届いているのだろうか。街で買う魚は肉よりも高価である、それを買ってもらうための提案や環境づくり、モチベーション(動機付け)は、適切に行われているのか…。
「コミュニケーション・ロス」の観点から、これからの「魚食普及」の在り方について、一度検証してみることが必要ではないだろうか。
「時間」マーケティング
生活者の魚食離れが、魚食全体の消費の低迷の原因とは思えないような動きもある。毎年行われる「目黒のさんま祭り」や漁連が開催する「シーフードフェア」などは、子どもから大人まで多くの来場者があり、大盛況だ。また、子どもに人気の回転寿司は、10年前の1.5倍(2016年)を売り上げている。私の故郷、仙台で回転寿司が登場したのが1968年、当時の子どもは刺身をあまり食べなかった記憶があるが、今は違う。魚好きの大人が食べる刺身を子どもも平気で食べる。居酒屋やレストランでも肉よりも健康的な魚が人気だ、魚は無くてはならないメインの商材である。このように魚食は広く普及しているのである。であれば、魚食離れは家庭での消費に的が絞り込まれてくる。イベントや外食などのハレの場では魚食が拡大し、日常(内食)では低下傾向にあるのは何故なのか、ここに問いを絞り込んで行けば、答えは見てくるはずである。
魚食といえば「鮮魚」。かまぼこや干物などの「水産加工食品」を思い浮かべる人は少ない。「鮮魚」は、働いているお母さんたちにとって一手間かかるという先入観がある。それでも「鮮魚」となれば、やはりいい魚を扱っている店を探すだろう。買った魚を電車に乗って持ち帰ることになれば、匂いや保存性も気になる。そして、子どもを引き取りに保育園へ。家に着いて一息いれる間も無く下ごしらえをし、調理、さらに後片付けが待っている。働く女性にとって「時間」を最優先するのは想像の通りである。普段の生活では「コンビニエント」が一番なのである。最近では夕食にも簡便さを求め、パスタなどに野菜を添えたワンプレートの食事も普通なのだ。
また、魚食離れの原因の一つとして、魚の骨と食べにくさの関係が指摘されるが、骨がある魚に触れることも子どもの食育の点からは重要なことだ。親に子どもの食事をケアする余裕の無さが、この問題の本質と推測できる。
しかし、そんな彼女たちでも、特別な日、特別なコトがあれば「時間」は惜しまない。
そこには魚の美味しさや健康との関わりを知り、子どもに食べさせてあげたいと思う母親としての彼女たちがいるのである。このように、魚を内食に取り戻すには、働く女性たちの「時間」が鍵となるのは間違いない。仕事、そして核家族という家族形態が、内食のスタイルを大きく変えたのである。
平成27年版の「働く女性の実情(厚生労働省)」によれば、これからの魚食を支えていく25?44歳の女性のうち、71.6%もの人が働いているのである。働く女性たちのライフスタイルに寄り添い、「時間」というファクターをマーケティングに加えることで、今まで見過ごしてきた魚食の機会を、掘り起こせるのではないかと思えてならない。
「働きながら子育てしてきた私も同感だわ」
「でも、時間のある高齢者はどうなの?」
義母は、キャリアウーマンの先駆けであり、元気な高齢者の筆頭でもある。
「魚屋で買っていた世代ですよね」
「魚屋が近所にないし、買い物や調理が億劫になってるんじゃないですか」
義母はすぐに畳み込んでくる。
「この間の講演でもEPAやDHAのことを話すと、高齢者にはとても反応がよかったのよ」
私も即座に応える。
「健康がこの世代のニーズだからですよ、問題は遠くのスーパーまで毎日行くかだと思いますよ」
納得していないようだ。
「今日はもういいけど、高齢者が買わなくなった理由を私にも分かるように説明してね」
義母は、ワインを飲み干し、終了のゴングを鳴らした。
義母とは言い合いになることもあるが、マーケッターとしては本音が聞き出せたかな、と思っている。議論は議論、時にはそこから面白いアイデアも生まれる。翌朝、お互い何もなかったかのように一緒にコーヒーを飲むのが和解の約束である。
鈴木たね子(すずき・たねこ)氏 プロフィール
農林水産省研究機関を経て、日本大学教授、国際学院埼玉短期大学教授。大日本水産会おさかな普及学術諮問会議座長、海洋開発審議会委員等を歴任。 現在は、国際学院埼玉短期大学客員教授、おさかなマイスター協会講師。「健康のための食生活」をテーマに、執筆、講演活動をしている。著書に『なぜ、魚は健康にいいと言われるのか?』(成山堂書)、『お魚を毎日食べて健康になる』(キクロス出版)など多数。